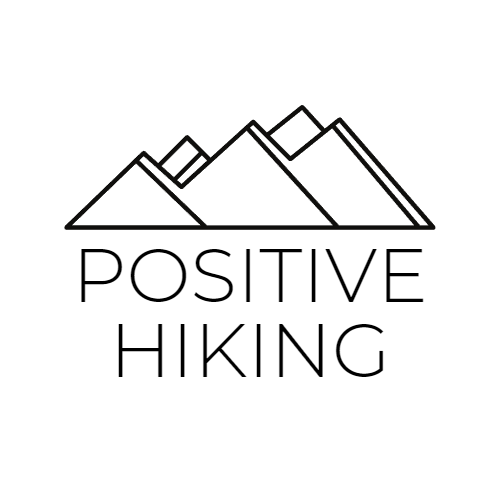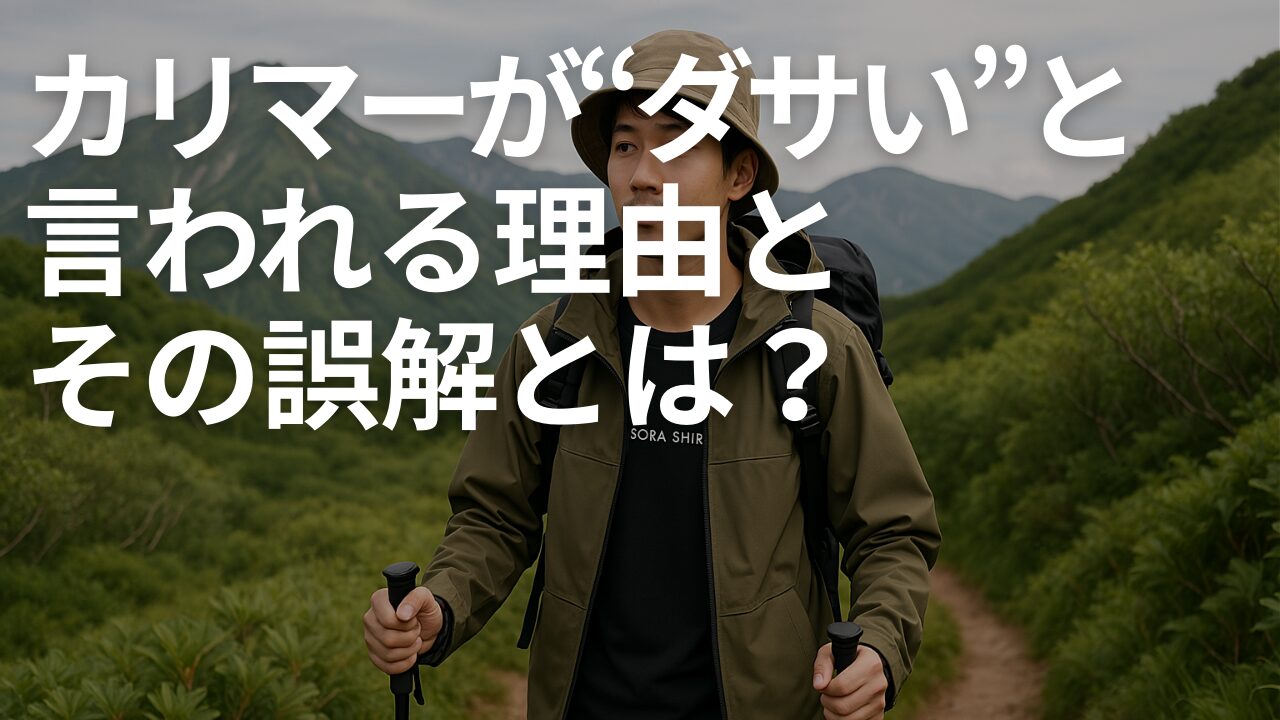「カリマーってダサくない?」
そんな声を一度でも聞いたことがある方へ。アウトドアブランドとして確かな歴史と信頼を持つkarrimor(カリマー)に対して、「地味」「古臭い」といった印象を持っている方もいるかもしれません。
しかし、そのイメージは本当に正しいのでしょうか?
本記事では、カリマーが「ダサい」と言われてしまう理由を整理しつつ、それが誤解であること、そしてむしろ「本物志向の人」に選ばれているブランドであることを丁寧に解説していきます。
読み終える頃には、あなたの中でカリマーの印象がきっと変わっているはずです。
カリマーが“ダサい”って本当?

「カリマーって、なんかダサくない?」
アウトドアブランドの話題になると、時折こんな声を耳にします。SNSや口コミでも、「機能性はいいけど、おしゃれではない」といったイメージを持たれていることも。しかし、果たしてそれは本当でしょうか?
カリマー(karrimor)は、イギリス発の老舗アウトドアブランド。登山家や軍関係者にも愛されるほどの本格的な性能を誇りながら、近年は都市生活にもフィットするアイテムを展開しています。
なぜ「ダサい」と言われてしまうのか?
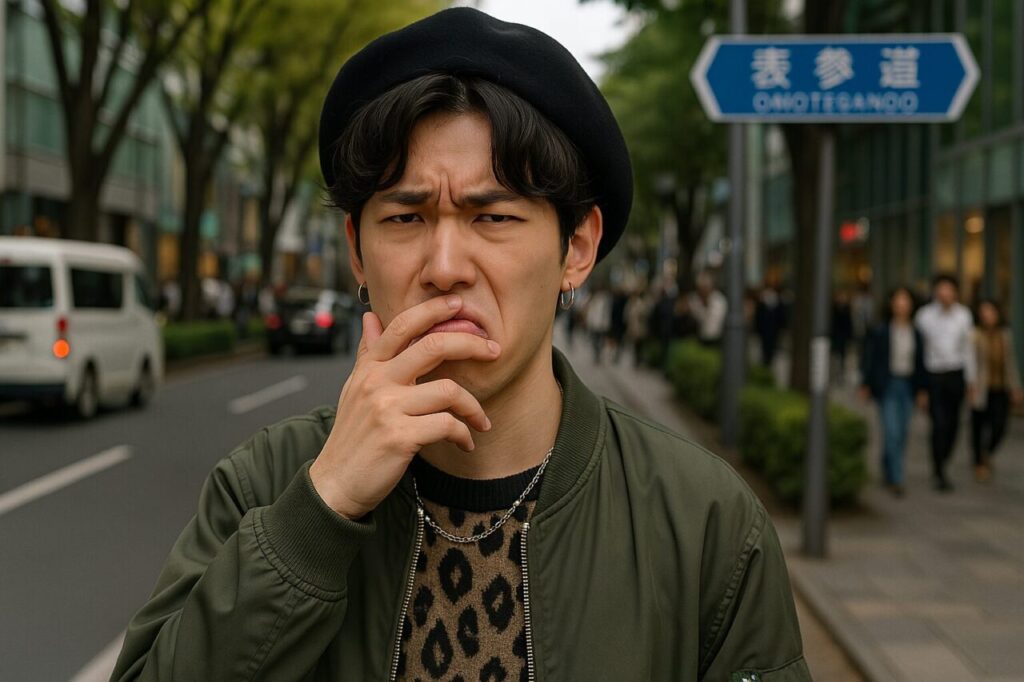
まず最初に確認しておきたいのは、「なぜカリマーは“ダサい”と思われているのか?」という疑問です。このイメージは本当に正しいのか、それともどこかで誤解が生まれているのか——。この記事では、そんなモヤモヤを一つずつ紐解いていきます。
この記事でわかること
- カリマーが“ダサい”と思われる理由
- 実は高機能&洗練されたアイテムがあるという事実
- 「通」が選ぶ理由と、カリマーをおしゃれに取り入れるヒント
カリマーが“ダサい”と言われる3つの理由
カリマーが「ダサい」と言われる背景には、いくつかの共通したイメージや先入観があります。しかし、それらは必ずしもブランド本来の価値を正しく評価したものではありません。ここでは、その主な理由を3つに分けて整理してみましょう。
理由1:デザインが地味で目立たない

多くの人が「ダサい」と感じる最初のポイントは、デザインが地味であるという印象です。
カリマーのアイテムは、派手なロゴやビビッドなカラーを多用することは少なく、機能性と耐久性を重視したシンプルなデザインが特徴です。
| 一般的なアウトドアブランド | カリマーの特徴 |
|---|---|
| 大きなブランドロゴ | 控えめなロゴや配色 |
| カラフルで目立つ配色 | アースカラーやモノトーン中心 |
| 流行を取り入れたシルエット | 実用性重視のベーシックな形 |
この「控えめさ」が、一部の人には「おしゃれじゃない=ダサい」と映ることがあるのです。
理由2:アウトドアブランドはファッションではないという先入観

もう一つの誤解は、「アウトドア=登山やキャンプ専用」という先入観です。
ファッション目的で選ぶブランドとして認知されていないため、街中で着ていると「山っぽい格好」と見られ、結果的に“おしゃれ”と見なされにくくなってしまいます。
しかし、実際にはアウトドアブランドは昨今のファッション業界でも注目されており、実用性とデザイン性の融合が再評価されているジャンルでもあります。
理由3:ファッション業界での露出が少ない
ノースフェイスやパタゴニアのように、ファッションメディアやコラボでの露出が少ない点も、カリマーのイメージ形成に影響しています。
話題になりにくいため、「知られていない=流行ってない=ダサい」と短絡的に捉えられがちです。
実際は、カリマーも限定アイテムやレーベル分けなどの工夫を行っていますが、それが広く知られていないことが、誤解を助長している要因といえるでしょう。
見た目だけで判断される悲しき“誤解”

つまり、カリマーが「ダサい」と言われるのは、
✔ 実用性重視のために見た目が地味
✔ アウトドアというカテゴリの先入観
✔ メディア露出の少なさ
といった複数の要素が絡み合って生まれた“誤解”です。
実は機能性重視の“プロ仕様”ブランド
「カリマー=ダサい」というイメージが先行してしまっていますが、実際にはカリマーはプロフェッショナルに選ばれてきた信頼のブランドです。この章では、その実力と背景を詳しく見ていきましょう。
カリマーの原点:登山家とともに歩んだ歴史

カリマーは1946年、イギリスで自転車用のバッグを製造するメーカーとしてスタートしました。その後、登山家や探検家の声を取り入れ、過酷な環境にも耐えられるバックパックやウェアの開発を行ってきました。
特に1960年代以降は、英国登山隊の公式装備として採用されるなど、本格アウトドアギアのパイオニアとして地位を確立。機能性に妥協せず、現場のニーズに真摯に応えてきた歴史があります。
イギリス軍や特殊部隊にも採用される信頼性
カリマーの「SF(スペシャル・フォース)」ラインは、イギリス軍の特殊部隊でも使用されており、その耐久性・信頼性は折り紙付きです。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 耐久性 | 高強度ナイロン素材を使用し、引き裂き・摩擦に強い |
| 機能性 | モジュール式ポケット、ハイドレーション対応など現場仕様 |
| 快適性 | 長時間の使用でも疲れにくい背面構造や重量バランス設計 |
つまり、カリマーは「実戦で使われている本物」のギアを展開しているブランドでもあるのです。
ファッションより“使えること”を重視した設計哲学

カリマーのアイテムは一見すると控えめなデザインが多いですが、それは「使えること」を最優先して設計されているからです。
たとえば:
- 軽量で動きやすい素材
- 無駄を省いた収納設計
- 過酷な環境にも対応できる耐久性
この“設計思想”を知ることで、見た目のシンプルさにも合理的な美しさがあることが見えてきます。
「知る人ぞ知る」的な魅力
一部の登山家やミリタリー愛好家からは、「カリマーを選ぶ人はわかってる」という声もあります。
派手さはないけれど、使ってみればわかる質の良さ。これがカリマーの魅力であり、ファッションよりも本質を重んじる人たちに選ばれてきた理由なのです。
カリマーは“玄人志向”の本格派ブランド

ファッションより“中身重視”の選択肢として再評価の余地あり
軍や登山家が信頼するハイスペック設計
機能性最優先の哲学があるからこそのシンプルさ
流行に左右されない、カリマーの“隠れたおしゃれ”要素
カリマーと聞いて、「ファッション性がある」と答える人はまだ少ないかもしれません。しかし実際には、カリマーはアウトドア用途だけでなく、日常生活で使いやすい“洗練されたアイテム”も展開しています。その代表が、2つのレーベル「Naturestyle」と「Lifestyle」です。
2つのレーベルに見るカリマーの二面性
カリマーは用途に応じた製品展開をしており、以下のように明確なコンセプトの違いがあります。
| レーベル名 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| Naturestyle | 本格アウトドア仕様。高機能素材・耐久性重視 | 登山、ハイキングなど |
| Lifestyle | 都市生活向けにデザイン。シンプルで上質な日常着 | タウンユース、通勤 |
特に注目すべきは「Lifestyle」レーベル。これが、カリマーに抱かれがちな“ダサい”イメージを覆すキーポイントです。
「Lifestyle」レーベルの魅力とは?

1. ミニマルで合わせやすいデザイン
「Lifestyle」は、派手さよりもシルエットの美しさや素材感に重きを置いています。カラーはブラック、ネイビー、カーキなど落ち着いたトーンが中心で、どんなスタイルにも合わせやすく、流行に左右されません。
2. 機能性とデザイン性のバランス
たとえば、撥水・防風などの機能がありながら、見た目はシンプル。つまり「見た目は都会的、中身はアウトドア」という、いいとこ取りの設計になっています。
3. “タイムレス”なスタイルを提案
一時的なトレンドではなく、長く使える普遍的なデザイン。これはファストファッションにはない、サステナブルな魅力でもあります。
レビューから見えるユーザーの評価

実際に「Lifestyle」レーベルを購入した人の声を見ると、その満足度の高さがわかります。
「仕事用のアウターとして買いましたが、軽くてシルエットもきれい。シンプルだから着回しやすいです。」
─ 30代男性・レビューより
「普段着として使ってます。アウトドアブランドっぽくなくて、でもちゃんと防風してくれるので助かる!」
─ 20代女性・レビューより
こうした声からも、「カリマー=山っぽい」のイメージを超えて、日常でもおしゃれに使えるブランドであることが伝わってきます。
「Lifestyle」レーベルを知ることで、カリマーのもう一つの顔——控えめだけど上質なおしゃれ——が見えてきます。
それは、“見せびらかすためのファッション”ではなく、“自分らしくあるためのスタイル”。流行を追わず、長く愛せる服を選びたい人にこそ、カリマーはフィットするのです。
なぜ「ダサい」という誤解が生まれるのか?
カリマーの実力や多様なレーベルを知ると、「ダサい」と言われていること自体が不思議に思えてきます。では、なぜそのような誤解が生まれてしまったのでしょうか?この章では、カリマーに対する“先入観”や“情報の偏り”といった背景を紐解いていきます。
1. 見た目だけで価値を判断してしまう風潮

現代のファッションは、「映えるかどうか」や「話題性のあるブランドか」が重視されがちです。そのため、ロゴやカラーが控えめで、主張しないデザインを持つカリマーは、一見して“地味”に見えることがあります。
特にSNS映えを意識する世代では、パッと見の派手さやトレンド感が重視される傾向が強く、機能性やブランドの哲学が見過ごされてしまいがちです。
2. メディアでの露出が少ない=流行ってない?

ファッションブランドが「おしゃれ」と認知されるには、雑誌・SNS・インフルエンサーなどを通じたメディア露出が重要です。しかし、カリマーはその点で控えめな姿勢を貫いており、他のアウトドアブランドのようにファッション業界と積極的にコラボすることは少ないです。
| ブランド | ファッションコラボ | 雑誌掲載頻度 | SNSでの話題性 |
|---|---|---|---|
| THE NORTH FACE | 高い | 多い | 非常に高い |
| Patagonia | 中程度 | 多い | 高い |
| karrimor | 低い | 少ない | やや低め |
このように、カリマーは“表に出る”タイプのブランドではないため、「知られていない=ダサい」という誤った認識が生まれやすくなってしまうのです。
3. ブランドの文脈が共有されていない
カリマーには「軍用規格の品質」や「登山家の信頼」といった豊かなストーリーがありますが、それが十分に伝えられていないことも問題です。
ファッション業界で評価されるブランドは、その“背景”や“哲学”が上手くブランディングされています。
一方でカリマーは、実直に“良いものを作る”ことに集中してきた結果、自らを語る機会が少なかったのかもしれません。
4. 「使う人」によって印象が変わるブランド

カリマーは、そのシンプルさゆえに着こなし方や使い方に“センス”が問われる一面もあります。
スタイリングの工夫がないと、ただの地味なウェアに見えてしまう可能性も。
つまり、「ダサく見えるか、おしゃれに見えるか」は、使う人次第という側面もあるのです。
「知らない」ことが誤解を生んでいる
- 見た目だけで評価されやすい現代の風潮
- 情報の不足や露出の少なさ
- ブランド背景の未認知
これらが複合的に重なり、「カリマー=ダサい」という誤解を生んでいます。しかし、それはカリマーの“本質”を知らないがゆえの偏見ともいえるのです。
結論:カリマーは“通”が選ぶ実力派ブランドだった
「カリマーってダサいの?」という問いに対する答えは、これまで見てきた通り、“誤解です”と断言できます。
確かに、カリマーは派手さやトレンド感では他のブランドに比べて控えめかもしれません。しかし、その裏には、本質を追求する姿勢・信頼性・使いやすさ・長く付き合えるアイテム作りといった、多くの魅力が詰まっています。
カリマーが「通好み」である理由
カリマーは、ブランド名やロゴで主張するのではなく、製品そのものの質で語るタイプのブランドです。
そのため、
- 機能性を重視する人
- トレンドより“自分らしさ”を大切にする人
- 長く使える道具や服を求める人
にとって、まさに「知る人ぞ知る名品」として愛されています。
ダサいかどうかは「どう使うか」で決まる

重要なのは、ブランドそのものではなく、自分がどう使いこなすかという視点です。
どんなに高級な服でも、着こなしや場に合わなければ魅力は半減します。逆に、カリマーのような実用的でシンプルなアイテムは、使う人のセンス次第で洗練された印象を生み出すことができます。
自分のスタイルに自信を持てる選択肢として
流行に流されるのではなく、「自分が本当に良いと思えるものを選びたい」。
そんな思いを持っている人にとって、カリマーは非常に心強いパートナーになるでしょう。
最後にポイントをまとめておきます。
| カリマーが選ばれる理由 | 説明 |
|---|---|
| 本格的な機能性と耐久性 | 登山家・軍も認めるプロ仕様 |
| シンプルで長く使えるデザイン | 流行に左右されず、日常に馴染むタイムレスな魅力 |
| ブランドの哲学と歴史 | 背景を知ることで、より愛着が湧く |
| “見せる”より“使う”を重視する価値観 | おしゃれとは“自分らしさ”の表現という本質的視点 |
最後に:カリマーを“知って選ぶ”時代へ
これまで「地味」とか「ダサい」と思っていた人も、カリマーの本当の魅力を知れば、印象は大きく変わるはずです。
おしゃれはトレンドだけじゃない。本質を知り、自分らしく選ぶことこそが、今の時代に求められるスタイルではないでしょうか。
「カリマーを選ぶ」という行為は、まさにその一歩。
あなた自身のスタイルを、より豊かにしてくれる選択肢のひとつとして、カリマーをぜひ見直してみてください。