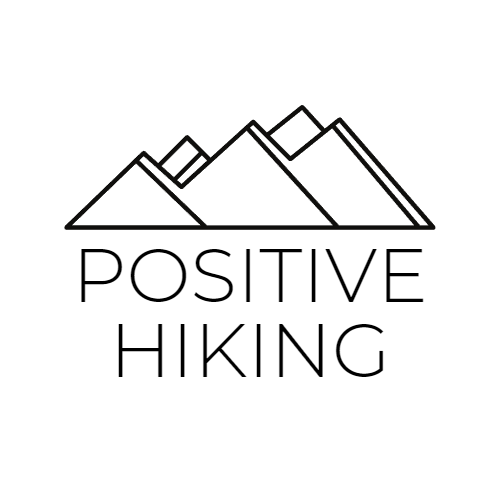「もっと楽に登れたらいいのに…」登山をしていて、そんな風に感じたことはありませんか?体力をつけたいと思っても、ジムに通うのは時間もお金もかかるし、継続するのも難しい。そんな悩みを抱える登山者にこそおすすめなのが「ランニング」です。
筆者も最初は半信半疑でしたが、週1〜2回の軽いラン習慣を取り入れただけで、明らかに登山中の息切れや脚の疲労感が軽減されました。
本記事では、登山に効くランニングの5つの効果と、初心者でも無理なく続けられる始め方、体験談も交えて詳しくご紹介します。
なぜ登山者にランニングがおすすめなのか

登山の体力づくりといえば、「とにかく山へ行く」「筋トレをする」といった方法が一般的ですが、実は日常的なランニングこそが、最も効率的で効果的なトレーニングのひとつです。特に平日に山へ行けない人にとって、走ることは貴重な“擬似登山”とも言えます。
ランニングが登山に有効な最大の理由は、心肺機能と筋持久力を同時に鍛えられる点にあります。登山では長時間にわたって坂道を登ったり、重い荷物を背負って歩いたりするため、酸素を効率よく取り込みながら、疲れにくい体を作ることが重要です。ランニングはそれを無理なく実現してくれるのです。
また、ランニングは時間やコストのハードルが低く、継続しやすいという大きなメリットがあります。特別な器具も必要なく、ウェアとシューズさえあれば自宅周辺でいつでも始められます。1回20分からでも十分効果が出るため、忙しい社会人や子育て中の人にもぴったりです。
これらの理由から、登山をもっと快適に楽しみたい人にとって、ランニングは“最短で効果が出るトレーニング法”だと言えるでしょう。
「登山とランニングで鍛えられる部位・効果の比較表」
| 項目 | 登山 | ランニング |
|---|---|---|
| 主に使う筋肉 | 大腿四頭筋・ふくらはぎ | 大腿四頭筋・ハムストリング |
| 心肺負荷 | 中〜高(時間による) | 中〜高(ペースによる) |
| 筋持久力 | 長時間歩行で向上 | 継続的な運動で向上 |
| 膝への負担 | 下山時に大きい | フォーム次第で軽減可能 |
| 補給の頻度 | 1〜2時間ごとに意識する必要 | 30〜60分ごとに必要(長距離) |
| 継続性・習慣化 | 山に行く必要がある | 自宅周辺で可能、習慣にしやすい |
登山に活きる!ランニングの5つの効果

1. 心肺機能が高まり、急登がラクになる
登山中、息が切れて立ち止まってしまう――そんな経験がある人は多いでしょう。これは単純に「体力がない」のではなく、心肺機能が追いついていないことが大きな原因です。ランニングは有酸素運動の代表格。継続することで、肺活量や酸素を効率的に体内へ取り込む力が高まり、登山中の呼吸が格段にラクになります。
筆者も以前は標高差の大きい山では頻繁に休憩していましたが、ランニングを習慣にしてからは歩きながら息を整えることができるようになり、登りのペースを安定させられるようになりました。結果として、時間に余裕が生まれ、景色を楽しむ心のゆとりも生まれます。
2. 脚力・筋持久力が向上して下山が安定する
登山で意外と疲れやすいのが「下山」です。膝が笑う、つま先が痛い、バランスが取りづらい……これらはすべて脚の筋持久力不足からくるもの。特に太ももやふくらはぎの筋肉が疲れてくると、足を踏ん張る力が落ち、転倒や膝の負担につながります。
ランニングは、登山で酷使される下半身を効率よく鍛えることができる運動です。特に長めのジョグや、やや起伏のあるコースを走ることで、登山に近い筋肉の使い方ができます。筆者自身、走るようになってから、下山後の疲労感や筋肉痛が大幅に減り、下山時の歩幅やリズムにも安定感が出てきました。
また、筋持久力がつくと長時間の行動でもバテにくくなり、体力の“最後のひと押し”に強くなるのも大きなメリットです。
3. 足さばきが良くなり、バテにくくなる
登山中に「段差でつまずく」「木の根に引っかかる」「思うようにリズムが取れない」といった経験はありませんか?これは、筋力だけでなく足さばき=体の使い方や反応速度の未熟さによるものです。
ランニングを継続すると、自然と脚の運びがスムーズになり、地面の変化に柔軟に対応できるようになります。特に舗装されていない不整地や階段のあるコースを走ることで、登山道の起伏にも強くなり、身体が無意識にバランスを取るようになるのです。
さらに、足運びが滑らかになると、余計な力みが減り、バテにくくなるという効果もあります。筆者も、岩場や下りでリズムが崩れがちだった場面で、ランニング習慣の効果を実感しました。結果として、登山中の消耗を抑えつつ、より快適な歩行ができるようになります。
4. 軽量志向・荷物選びの感覚が変わる
ランニングを習慣にすると、自然と「身軽であることの快適さ」に気づくようになります。たとえば、ポケットにスマホやボトルを入れて走るだけでも「重さ」や「揺れ」が気になり、持ち物の必要・不要を敏感に判断できるようになるのです。
この感覚は、そのまま登山装備の見直しにもつながります。「本当にこのレインウェアは必要?」「このギアはもっと軽量化できるのでは?」といった意識が芽生え、装備の取捨選択が洗練されていきます。
筆者も以前は念のため…と道具を詰め込んでザックがパンパンでしたが、ランニングを始めてからは**“使うかどうかわからない物”を削る勇気**がつき、行動中の疲労がかなり軽減されました。
もちろん、安全を損なわないことが前提ですが、「軽量で快適な登山スタイル」を目指すうえで、ランニングは感覚を研ぎ澄ますトレーニングにもなるのです。
5. 補給の意識が身について行動食の工夫が進む
登山では「気づいたらエネルギー切れで動けなくなっていた」という経験をする人も少なくありません。これは、空腹や疲労を自覚する前に適切な補給ができていないことが原因です。
ランニングを継続すると、この**“補給のタイミング”に対する意識が自然と高まります**。
特に長めのランや坂道を含むコースでは、走りながら水分やエネルギーを摂らないとパフォーマンスが明らかに落ちてくるため、補給の重要性を体で覚えます。これにより登山でも、「30分〜1時間に一口の補給を意識する」「こまめな水分摂取を忘れない」といった習慣が身につきます。
さらに、筆者はランニング中に試したエネルギージェルや塩分タブレットの中から、登山でも使えるものを発見し、行動食の選び方に幅が広がりました。食べやすさ、携帯性、消化の速さ――ランナー目線の視点が、登山における補給戦略をより洗練されたものにしてくれます。
登山者がランニングを始めるときの注意点

ランニングは手軽に始められる反面、最初のやり方を間違えるとケガや挫折につながりやすい運動でもあります。特に登山者は「体力に自信がある」ことでつい飛ばしがちですが、登山とランニングでは使う筋肉や衝撃のかかり方が異なるため、まずは週1〜2回・20分程度の軽いジョグからスタートするのがおすすめです。
初日は「走る」というより「歩く+30秒だけ走ってみる」くらいでも十分。翌日に筋肉痛が出ても驚かず、体が慣れるのを待つことが継続のコツです。
また、シューズ選びも重要です。登山靴とは異なり、クッション性と軽さを兼ね備えたランニングシューズやトレランシューズを選ぶことで膝や足首への負担を大きく減らせます。
無理せず、楽しめるペースから始めましょう。継続こそが最大の効果を生むトレーニングです。
登山のための効果的なランニングメニュー

登山に活かすためのランニングは、競技志向のトレーニングとは異なり、無理なく継続できることが最優先です。登山に必要な心肺機能・筋持久力・リズム感をバランスよく養うために、以下のようなメニューが効果的です。
まず、平日は30分程度のゆるジョグを週1〜2回。ペースは「会話できる程度」が理想で、疲れを溜めずに心肺機能を高めます。時間が取れない日は、10分程度のウォーキング+ストレッチでも構いません。
週末に時間が取れる場合は、起伏のあるコース(階段や坂道など)を歩き交えながら走る「ビルドアップ走」や、「早歩き+ラン」の繰り返しもおすすめ。これは実際の登山に近い動きを養えます。
さらに、**インターバル走(速め→ゆっくりを交互に)**は、急登やラストの踏ん張りに強くなる実戦的メニューです。登山本番に向けた「心拍数の使い方」を体で覚えられます。
| 項目 | 内容例 | ポイント |
|---|---|---|
| 平日メニュー | 30分のゆるジョグ(週1〜2回) | 会話できるペースで心肺に負担をかけすぎない |
| 休日メニュー | 起伏のある道でのビルドアップ走 | 登山に近い筋力とリズムを養える |
| 時間がない日 | 10分ウォーク+ストレッチ | とにかく続けることが大事 |
| 応用メニュー | 階段ダッシュ/インターバル走 | 急登・踏ん張りの強化に有効 |
実際にやってみてどう変わったか(筆者の体験談)
筆者はもともと登山が中心でしたが、コロナ以前からランニングも継続しており、10km程度の距離は無理なく走れるようになっていました。ある時期から「もう少し登山に活きるような走りを」と考え、坂道やインターバルなど、強度を上げたトレーニングを取り入れ始めました。
その結果、最も実感したのが膝への負担の軽減です。以前はフルマラソンの終盤や登山の下りで膝が痛くなっていたのですが、今ではフルを走っても膝が気にならないレベルに。登山でも下山が圧倒的に楽になり、行動時間も伸びました。ランニングが、登山にとって大きな“土台”になっていることを実感しています。
まとめ

登山のために体力をつけたいなら、ランニングは最も手軽で効果的なトレーニングのひとつです。心肺機能や脚力の向上はもちろん、足さばきや補給の感覚まで、登山に直結する“実用的な体力”が自然と身につきます。
筆者自身も、ランニングの強度を高めることでフルマラソンでの膝痛を克服し、登山中の疲労も大きく軽減されました。
無理なく続けられる方法からスタートし、ランニングを登山の相棒に育ててみてはいかがでしょうか。