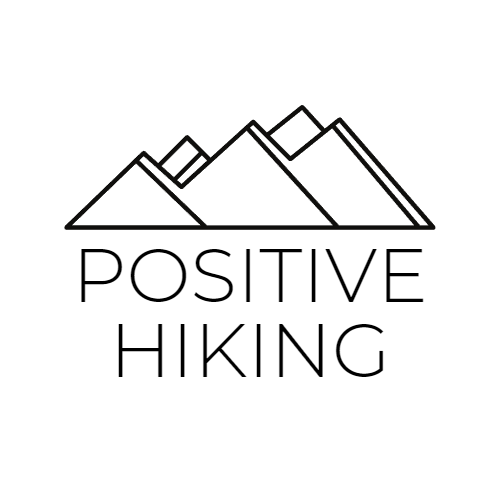登山と聞くと「登りが一番大変」と思われがちですが、実は最もケガや事故が多いのは“下山”です。
疲れがたまった状態で下り坂を進むのは、想像以上に体に負担がかかり、注意力も低下しがち。
この記事では、なぜ下山が危険なのか、そして安全に下山するためのコツについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。
無事に山を楽しんで帰るために、ぜひ最後までチェックしてみてください。

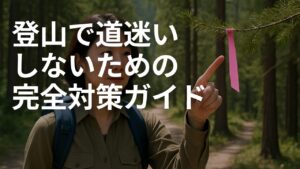
実は危険!下山で事故が多い理由
登りを終えたあとの「下山」は、つい安心してしまうもの。
しかし、ここで油断すると転倒やケガ、さらには遭難につながるリスクが一気に高まります。
なぜ下りのほうが危ないのか、3つのポイントに分けて解説します。
① 疲労がピークに達している

登頂後の下山時は、体力が大きく消耗しています。
筋肉の疲労が蓄積していると、足元がふらつきやすくなり、ちょっとした段差や石にもつまずきやすくなります。
また、判断力や集中力も低下するため、ルートを間違えたり、危険箇所に気づきにくくなることも。
「下山は身体的にもメンタル的にも一番きつい時間帯」だと意識することが大切です。
② 足場の悪さを見落としやすい
登りでは一歩ずつ慎重に足元を見ていたのに、下りになるとスピードが出やすくなり、足場への注意が疎かになりがちです。
特に、濡れた岩場、落ち葉に隠れた石、ぬかるんだ地面などは転倒リスクが高いポイント。
「まだ大丈夫」と思って油断すると、一瞬でバランスを崩してしまう危険があります。
③ 油断しやすい心理状態
登頂という大きな目標を達成したあと、どうしても「もう終わった」という達成感から、気持ちが緩みがちです。
下山は「帰るだけ」という意識が事故を招く最大の落とし穴。
実際、登山での滑落事故や捻挫の多くが、下山中に発生しているというデータもあります。
最後まで「気を引き締める」ことが、無事に山から帰るためのカギになります。
安全に下山するための3つのコツ
下山時の事故を防ぐためには、「慎重な行動」と「ちょっとした工夫」がとても大切です。
ここでは、初心者でもすぐに実践できる安全対策を3つ紹介します。
① ペースを意識して「急がない」
下山中に最も注意すべきは「スピードの出しすぎ」です。
特に疲れてくると、無意識に歩幅が広くなったり、体重を前に預けてしまいがち。
**「小またで一歩ずつ、足を置く場所を確認しながら歩く」**これだけで、転倒リスクは大幅に減らせます。
周囲のペースに惑わされず、自分のリズムを守ることを心がけましょう。
② ストックやサポートギアを活用

トレッキングポール(登山用ストック)を使うと、下りの膝や足首への負担を大幅に軽減できます。
また、滑りやすい斜面や段差のある場所では、ポールでバランスを取りながら慎重に降りると安心です。
**「初心者こそ道具を上手に使う」**ことが、安全登山の第一歩です。
③ 疲れを感じたらすぐ休憩
疲労を感じたまま歩き続けると、集中力が切れやすくなり、事故のリスクが一気に高まります。
「まだ大丈夫」ではなく、少しでも疲れたと感じたら迷わず立ち止まる習慣を持ちましょう。
水分補給や軽いエネルギー補給も忘れずに行い、体力をこまめにリセットすることが大切です。
まとめ

登山では「登りがきつい」と感じるものですが、実際に事故が多いのは下山です。
疲労の蓄積、足元の見落とし、油断による注意力の低下——。
これらが重なったとき、思わぬケガや滑落事故が起きてしまいます。
安全に下山するためには、
- スピードを抑えて慎重に歩く
- ストックなどのサポートギアを活用する
- 疲れたらすぐ休憩を取る
といった基本を守ることが何より大切です。
「登山の本当のゴールは、無事に帰ること」。
その意識を持って、最後まで気を抜かず、安全な下山を心がけましょう!