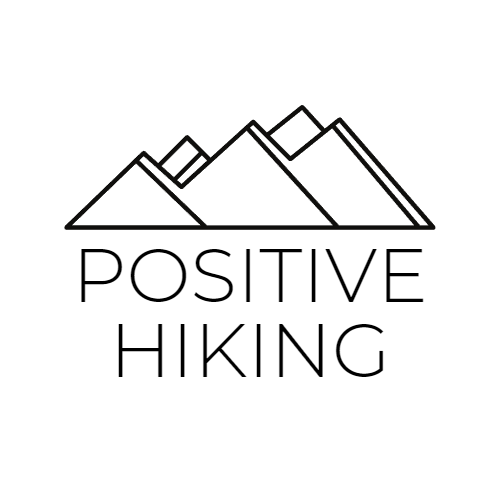登山中に実践したい道迷い対策

事前にいくら準備を整えていても、登山中の判断ミスや油断によって道に迷ってしまうことはあります。
ここでは、実際に登山中に気をつけたい「道迷いを防ぐ行動習慣」を紹介します。
分岐では必ず立ち止まり、地図やアプリで確認する
最も多い迷い方が「分岐点での誤進入」です。道が二股、三股に分かれている地点では、必ず一度立ち止まり、進む方向を地図やアプリで確認しましょう。
何となく流れで歩き続けてしまうと、気づかないうちに本来の登山道を外れてしまうことがあります。
また、分岐の直前で「ここ分かれ道っぽいな」と感じたら、すぐにマークしておく習慣を持つと、戻る判断もしやすくなります。
ピンクテープ・道標を見逃さない
日本の登山道には、木の枝や幹にピンク色のテープ(目印テープ)が取り付けられていることが多く、ルートを示す大事な手がかりとなります。
歩きながら、「さっき見たテープからあまり時間が経ってないか?」と常に意識しておくと良いでしょう。
ただし、間違った方向に付けられているテープも存在するので、「テープがあるから安心」と盲信せず、常に地図やGPSと照合しながら進むことが重要です。
こまめに現在地を確認する
道に迷ったとき、どこで間違えたかを把握していれば、すぐに引き返す判断ができます。
そのために必要なのが、「現在地のこまめな確認」です。
具体的には、
- 地図とコンパスで、今いる尾根や谷の形を見比べる
- アプリ(YAMAPなど)で現在位置と進行方向を確認
- 地形と地図の照合をする
など、定期的に立ち止まって確認する習慣を持ちましょう。
特に見通しの悪い樹林帯では、つい「一本道だから大丈夫」と油断しがちですが、迷いやすい地点でもあります。
見慣れない風景が続いたらすぐに引き返す
「あれ?こんな道だったっけ?」と違和感を覚えたら、迷い始めているサインです。
そう感じた時点で、すぐに引き返すのが正解です。
「この先で道が合流してるかも」と安易に進み続けるのは非常に危険です。迷っている最中は判断力が鈍りがちで、誤った方向へさらに深く進んでしまう可能性が高くなります。
1本の道を5分〜10分進んでも道標やテープが見つからない場合は、すぐに来た道を引き返し、確実なポイントまで戻るようにしましょう。
グループ登山時の「意思確認」も重要
複数人で登山している場合も油断は禁物です。ありがちなのが、「先頭の人についていけば安心」と思ってしまうこと。
しかし先頭の人も道を間違えることは当然ありえます。
定期的に「今どこ?」「ここで合ってる?」と声を掛け合って確認することが、グループ全体の安全を守ることにつながります。
特に体力差があるグループでは、後方の人がルートを見失ってしまうケースもあるため、分岐や広い場所では一旦集合するなどの工夫も必要です。
もし道に迷ってしまったらどうする?

万全の準備と慎重な行動をしていても、山では「想定外」がつきものです。
それが道迷いだった場合、慌てず冷静に行動することが命を守る鍵となります。
ここでは、道に迷ったときに取るべき行動と絶対に避けたいNG行動を具体的に紹介します。
原則は「引き返す」
登山中に「道を間違えたかもしれない」と思った時点で、まず最初に検討すべき行動は「引き返すこと」です。
数分前に通った確実なポイントまで戻ることで、道を修正できるケースは多いです。
- 「最後に道標を見たのはどこか?」
- 「登山道に間違いないと確信していたのはどの地点か?」
を思い出し、そこまで戻ることで、判断材料が増えます。
「先に進めば何か見つかるかも」という希望的観測で行動すると、さらに深い山奥に入り込み、事態が悪化します。
むやみに動き回らない
「完全に道に迷った」と確信したら、それ以上むやみに動くことは避けましょう。
パニック状態で動くと、
- 崖や沢に入り込んで危険にさらされる
- 現在地がわからなくなって救助が困難になる
といったリスクが高まります。
安全な場所に腰を下ろし、まずは深呼吸して落ち着くことが大切です。
精神的に冷静さを保てるかどうかが、その後の判断に大きく影響します。
スマホで現在地を確認し、電波があれば連絡
もし電波が入るようであれば、以下の順で行動しましょう。
- 登山アプリ(YAMAPなど)で現在地を確認
- Googleマップでも現在地が出るかチェック
- 家族・知人に「道に迷った」ことを伝える
- 必要に応じて110番または山岳救助へ連絡
山では「圏外でも一瞬だけ電波が通じる場所」があることもあるため、移動せずにスマホを高く掲げたり、電源を入れ直したりして電波を探すのも有効です。
登山届や登山アプリの軌跡が救助に役立つ
事前に登山届を出していれば、行方不明になった場合でも「どの山の、どのルートを通っている予定だったか」が分かるため、救助活動が迅速に行われやすくなります。
また、YAMAPなどの登山アプリで登山記録(軌跡)を残しておくと、たとえ圏外でもスマホのログから位置を特定できる場合があります。
2023年には、YAMAPのログをもとに早期に発見された事例も報告されています。
ヘッドライト・防寒具でビバークに備える
夕方以降に道に迷った場合は、その場でのビバーク(緊急的な野宿)を視野に入れる必要があります。
そのために備えておくべき装備は以下の通りです:
ヘッドライト(手元が空くため懐中電灯より有効) エマージェンシーシート(保温・防風) 防寒着(特に標高が高い山では体温低下が致命的)
夏場でも、標高が1,500mを超えると夜は一気に冷え込みます。
道に迷って暗くなったら「下山を試みない」のが鉄則です。
無理な下山は事故のもと
「何としてでも家に帰らなきゃ」と焦る気持ちは自然ですが、無理に下山しようとすることが一番危険です。
斜面を下るうちに、
急傾斜で足を滑らせる 沢に転落する さらにルートを見失う
といった二次災害につながる恐れがあります。
夜間や視界の悪い状況では、動かず、朝まで待機する方が安全である場合も多いです。