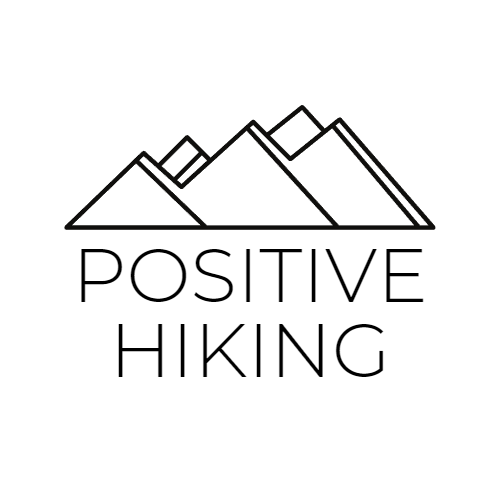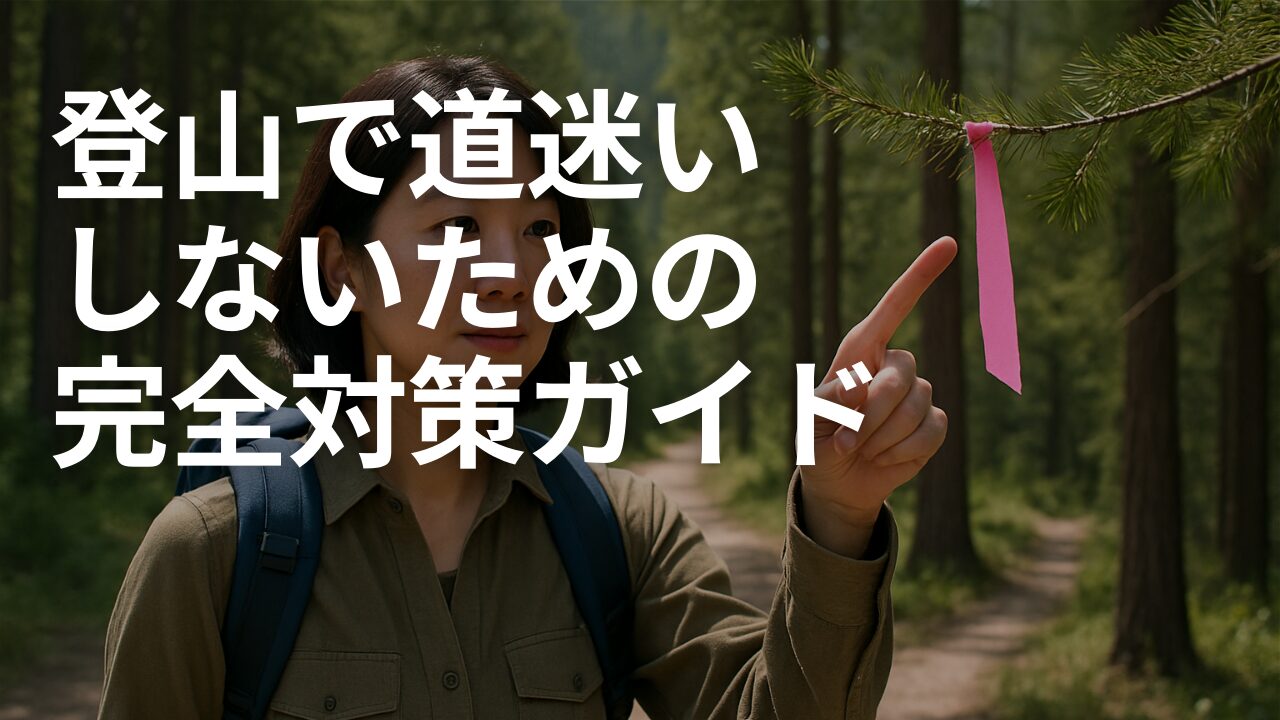「登山は道があるから迷わない」――そう思っていませんか?
実は、登山中の遭難原因の中で最も多いのが“道迷い”です。分岐での判断ミス、踏み跡の誤認、日没による視界不良など、少しの油断が命取りになることも。本記事では、登山初心者にもわかりやすく、道に迷わないための準備・行動・装備を徹底解説。もし迷ってしまった場合の対処法まで紹介しています。「登山をもっと安全に楽しみたい」という方は、ぜひ最後までお読みください。
なぜ登山では道迷いが起きるのか?

道迷いは登山遭難の主要原因
登山中の遭難事故の中で、最も多い原因の一つが「道迷い」です。警察庁の統計によれば、近年の山岳遭難事故の約4割が道迷いによるものと報告されています。これは、滑落や転倒といった他の事故原因を上回る割合であり、登山者にとって道迷いがいかに重大なリスクであるかを示しています。
道迷いが発生する主な要因
道迷いが発生する背景には、以下のような要因が挙げられます。
- 分岐点での判断ミス:登山道の分岐点で正しいルートを選択できず、誤った方向に進んでしまうケースです。
- 踏み跡の誤認:動物の通った跡や過去の登山者が作った非公式な道を正規の登山道と勘違いして進んでしまうことがあります。
- 視界不良:霧や雨、夕暮れ時などで視界が悪くなり、道標や目印を見落としてしまうことが原因となります。
- 過信と準備不足:登山経験が豊富な人でも、地図やコンパスを持たずに登山を行い、結果として道に迷ってしまうことがあります。
道迷いのリスクを軽視しない
道迷いは、単なる方向の間違いではなく、命に関わる重大なリスクです。特に、携帯電話の電波が届かない場所や、天候が急変する山岳地帯では、道に迷うことで救助が遅れ、低体温症や脱水症状などの危険が高まります。また、道に迷ったことでパニックに陥り、さらに状況を悪化させることもあります。
このようなリスクを避けるためには、事前の準備と知識が不可欠です。次章では、登山中に道迷いを防ぐための具体的な対策について詳しく解説します。
登山で道に迷わないための事前対策

登山で道に迷わないためには、「現地に行ってから考える」では遅すぎます。
最も大切なのは、登山前にどれだけ準備ができているかです。ここでは、初心者でもすぐに実践できる事前対策を6つ紹介します。
1. 紙の地図とコンパスを携帯し、使い方を習得する
スマホが普及した今でも、紙の地形図とコンパスは必須装備です。スマホのバッテリー切れや故障、圏外などのリスクに備え、アナログな道具も必ず携行しましょう。
特に登山初心者にとって、地図読みは敷居が高く感じられるかもしれませんが、登山地図にある等高線や尾根・谷の読み取り方、コンパスによる進行方向の確認など、基本だけでも覚えておくと安心です。
→ 参考:日本山岳ガイド協会主催の「読図講習会」などを受講するのもおすすめです。
2. 登山アプリ(GPS)を活用する
最近では多くの登山者が使っている登山用GPSアプリ(例:YAMAP、Geographica、ヤマレコなど)は、道迷い防止に非常に役立ちます。
YAMAPは特に初心者に人気で、事前に地図をダウンロードしておけば、圏外でも自分の現在地が確認できます。ルートを外れると通知してくれる機能もあり、安心感があります。
また、事前に歩くコースをアプリで確認し、過去の登山者のログや注意点などもチェックしておくことで、迷いやすいポイントを事前に把握することができます。
3. コースタイムと日の入り時刻を調べておく
道に迷いやすくなる要因のひとつが「時間の余裕がないこと」です。日が暮れると視界が悪くなり、道標や踏み跡が見えにくくなるため、迷いやすくなります。
登山前には、
コースタイム(標準的な所要時間) 日の入り時刻 自分の体力や歩行スピード
を加味して、下山時刻を逆算しておくことが重要です。
また、Googleで「〇〇山 日の入り」などと検索すれば、地域ごとの日没時間も簡単に確認できます。
4. 単独登山は避け、できる限り複数人で登る
初心者や不慣れな山では、単独登山は非常にリスクが高いです。道迷いだけでなく、ケガや体調不良に見舞われた際に助けが呼べない可能性があるためです。
複数人で登る場合は、お互いに地図を見て確認しあったり、迷いそうなポイントで相談できることが、道迷い防止につながります。
どうしても単独で登る場合は、登山届の提出と家族・友人への連絡を徹底しましょう。
5. 迷いやすいポイントを事前に把握する
ルート上の「迷いやすいポイント」を事前にチェックすることは、非常に効果的な対策です。
具体的には、
- 分岐が多い場所
- 踏み跡が交差するエリア
- 林道や作業道と交差する地点
などは、道に迷いやすいポイントです。登山アプリで他の人の記録を参考にしたり、ブログや山行記録を検索して事前に調べておくと、現地での判断力がぐっと上がります。
6. 登山届を提出する(義務化の自治体もあり)
万が一道に迷ったとき、登山届を提出しているかどうかが生死を分ける場合もあります。
登山届には「予定ルート」「登山者の名前」「緊急連絡先」などを記載します。提出先は山域によって異なりますが、最近はYAMAPや登山ポータルサイト(コンパス等)からオンラインで簡単に提出可能です。
例えば、長野県や北アルプスの一部では登山届提出が義務化されています。安全意識の高い登山者ほど、登山届をきちんと提出しています。