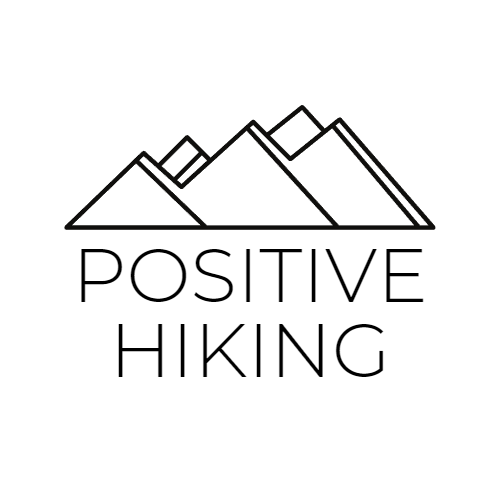「登山に傘なんて邪道では?」と思う人もいるかもしれません。ですが近年、あえて“折りたたみ傘”を登山装備に加える登山者が増えています。一方で、昔から登山の雨対策の王道といえば「レインウェア」ですよね。
どちらが正解なのか——。
実はこのふたつ、それぞれに明確なメリットとデメリットがあります。
今回は「折りたたみ傘」と「レインウェア」を比較し、登山でどちらを選ぶべきか、場面ごとの使い分け方を解説します。
それぞれのメリットとデメリット
登山中の突然の雨に備えて、どんな装備を持つべきかは悩ましいところ。ここでは「折りたたみ傘」と「レインウェア」、それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。
折りたたみ傘の特徴

【メリット】
- 通気性が良く蒸れない
レインウェアと違って風通しが良く、汗をかきにくいため、夏場の行動時に快適です。 - ザックを降ろさずにサッと使える
突然の小雨にも、傘ならすぐに対応可能。レインウェアのように脱ぎ着の手間がありません。 - 日差し除けとしても活躍
晴天時には日傘としても使えるため、熱中症予防にも一役買います。
【デメリット】
- 風に弱く壊れやすい
強風の稜線などでは使い物にならないことも。耐久性の面では不安が残ります。 - 片手がふさがる
傘を持つことで片手が使えなくなり、バランスを取る必要がある登山道では危険な場合も。 - 岩場や狭い登山道では邪魔になる
特に両手を使う場面では、傘は行動を制限してしまいます。
レインウェアの特徴

【メリット】
- 両手が自由で安全性が高い
着るタイプなので両手が使え、岩場や木の根が多いルートでも安心して歩けます。 - 風雨をしっかり防げる
上下セットで身体を完全に覆うため、強い風や冷たい雨でも体温を奪われにくくなります。 - 登山用は耐久性も高い
山岳メーカーのレインウェアは破れにくく、長く使える点もメリットです。
【デメリット】
- どうしても蒸れる
いくら高機能でも、汗を完全に逃すことはできません。夏は特に不快感が強まります。 - 脱ぎ着が面倒
特にザックを背負ったままだと着替えにくく、急な雨であたふたすることも。 - かさばる場合もある
軽量化は進んでいるものの、上下セットは折りたたみ傘より収納スペースを取ります。
登山ではどう使い分けるべき?
どちらにも一長一短がある「傘」と「レインウェア」。
大切なのは、「登山スタイルや天候に応じた使い分け」です。
状況別のおすすめ
以下のように、登山の目的やルートによって適した装備は異なります。
- 日帰りハイク・晴れ予報の日
→ 折りたたみ傘が活躍。軽くて通気性もよく、休憩時や日差し除けにも便利です。軽量レインウェアを予備で持つのが安心。 - 風の強い稜線歩き・天候不安定な日
→ レインウェアが必須。傘は役に立たず、逆に危険。身体を守るレイヤリングとしても機能します。 - 樹林帯中心のルート・小雨程度の予報
→ 傘でも対応可能。風が弱く、道幅も広い場所なら傘の方が快適なこともあります。
実際の登山者の声
登山者の間でも「傘派」と「レインウェア派」に分かれることが多く、それぞれ納得の理由があります。
- 「夏の低山では傘が一番快適。蒸れずに済むのがありがたい」
- 「岩場や急登があると傘は邪魔。結局レインウェアに頼る」
- 「両方持って行って、状況で使い分けてる」
このように、現場のリアルな声を参考にしながら、自分の登山スタイルに合った装備を選ぶことが重要です。
結論(まとめ)

「登山での雨対策=レインウェア」が定番ではありますが、折りたたみ傘にも意外な魅力があります。
両手が自由になる安心感や、悪天候でも身体をしっかり守れるレインウェア。
一方で、素早く使えて蒸れず、夏の暑さ対策にもなる折りたたみ傘。
大切なのは「どちらを選ぶか」ではなく、状況に応じて使い分けること。
日帰りの軽登山や低山では傘が快適な場面も多く、一方で稜線や悪天候にはレインウェアが欠かせません。
「晴れ予報だけど一応…」というときには、軽量な折りたたみ傘をザックに忍ばせておくのも、登山者の新しい選択肢かもしれません。