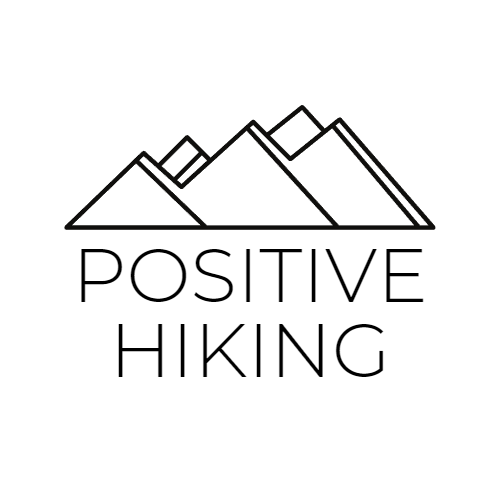登山靴の常識を覆す──そんな一足に出会いました。
登山歴10年以上、これまでトレランシューズや軽登山靴を愛用してきた私が、初めて「ベアフットシューズ」で登山に挑戦。選んだのはMERRELL(メレル)のVapor Glove 6。
今回は兵庫県・摩耶山の上野道〜掬星台〜穂高湖〜シェール槍というルートで、その“素足感覚”をリアルに体験してきました。
「足裏で地面を感じるって、こんなに楽しいのか!」
そんな驚きと気づきに満ちた一日を、実体験ベースで詳しくお伝えします。
登山歴10年の筆者が、初めての「ベアフットシューズ」に挑戦

登山を始めてから気がつけば10年以上。これまでに登った山は、近場の低山からアルプスの稜線歩きまで、日帰り・縦走・テント泊とスタイルも様々です。私自身の登山スタイルは「歩くことを楽しむ」タイプ。ガツガツとスピードを競うのではなく、自然と対話するように、風や匂い、足元の変化を感じながら歩くのが好きです。
ギアにもそこそここだわりはありますが、「快適であること」が第一条件。登山靴もこれまでにいくつか試してきましたが、基本はローカットの軽登山靴を好んで使ってきました。理由は、足元が軽くなることでより自由に歩けるから。とはいえ、これまで「ベアフットシューズ」には一度も手を出してきませんでした。
それが今回、ついにベアフットシューズの世界に足を踏み入れることになったのです——。

なぜベアフットシューズを試そうと思ったのか

これまで私の登山スタイルでは、基本的にトレイルランニング用のシューズを使っていました。走るほどではないけれど、軽くてグリップの効いたトレランシューズは歩きやすく、特に整備された登山道や低山では相性抜群。ただし、岩場やゴツゴツとした難所のある山では、ワークマンの登山靴を使用するなど、用途によって履き分けていました。
そんな私が「ベアフットシューズ」に興味を持ったのは、あるミニマリストの方のYouTube動画がきっかけです。その方は登山もされていて、「ベアフットシューズで自然と一体になれるような感覚が味わえる」と語っていました。さらに、道具を減らし、必要最小限で暮らすというミニマリズムの哲学にも共感。登山をよりシンプルに、より直感的に楽しむ手段として、ベアフットシューズに強く惹かれるようになったのです。
「登山=重装備」という従来のイメージを一度リセットして、もっと自由に、もっと感覚的に山を歩いてみたい。そんな気持ちが高まり、ついにベアフットシューズを取り入れてみることに決めました。
Vapor Glove 6を選んだ理由

ベアフットシューズに興味を持ち始めた頃、まず行ったのはネットでの情報収集。レビュー記事や比較サイト、そしてYouTubeでの使用レポートを片っ端からチェックしました。中でも特に気になったのが、Vivobarefootの「プライマストレイルニット FG」と、MERRELLの「Vapor Glove 6」の2モデルでした。
Vivobarefootはベアフットシューズ界隈での評価も高く、「足を鍛える」「本当に裸足に近い感覚が得られる」といった口コミが多く見受けられました。見た目もスタイリッシュで、山にも街にも履いていけそうな雰囲気。ただし、近所に取り扱っている店舗がなく、試し履きができないという点が大きなネックでした。初めてのカテゴリのシューズを、実物を見ずに買うのはやはり不安があり、今回は見送ることに。
一方、MERRELLの「Vapor Glove 6」は実際に店舗で試し履きできたのが大きなポイント。私の足との相性もチェックでき、「これはいけそうだ」と実感できたのが決め手になりました。さらに、価格もVivobarefootより手頃で、購入のハードルが低かったのも魅力。ベアフットシューズ初心者としては、まずは実際に体験してみることが大事。そう思って、MERRELLの一足から始めてみることにしました。
MERRELL Vapor Glove 6ってどんなシューズ?

MERRELL(メレル)はアメリカ発のアウトドアブランドで、登山靴やハイキングシューズでよく知られていますが、その中でも「Vapor Glove 6(ベイパーグローブ 6)」は、極限まで足裏感覚にこだわったベアフットシューズです。
以下が主なスペックと特徴です。
- 重量:片足 約150g(メンズ27cmの場合)
とにかく軽い。箱から出した瞬間「これ、スリッパ?」と思ってしまうほどの軽さです。 - ソール:Vibram® EcoStepソール
Vibram(ビブラム)社製の薄いラバーソールが採用されており、グリップ力と柔軟性を両立。EcoStepはリサイクル素材を使っており、環境にも配慮されています。 - ドロップ(かかととつま先の高低差):0mm
一般的なランニングシューズは10mm前後のドロップがありますが、Vapor Glove 6は完全なフラット設計。裸足に近い自然な姿勢での歩行を促します。 - アッパー素材:リサイクルメッシュ
通気性が高く、蒸れにくい。軽量化にも貢献していて、夏場の使用にもぴったり。 - インソール:極薄EVAフォーム
クッション性はほぼ皆無。ただし、そのぶん足裏感覚をダイレクトに感じられます。
このシューズの最大の特徴は、やはり「足と地面の距離の近さ」です。歩くたびに、足裏から伝わる微細な情報が脳に届き、まるで自然と一体になったような感覚を味わえます。
通常の登山靴との違いとは?
登山靴といえば、しっかりとしたソール、足首まで覆うアッパーカット、防水性、そしてクッション性などが特徴です。足を守り、長時間の歩行による疲労を軽減するために設計された機能的な装備ですが、Vapor Glove 6のようなベアフットシューズは、これらとは真逆の発想で作られています。
1. ソールの厚さとクッション性の違い

一般的な登山靴やトレッキングシューズは、厚みのあるソールで地面の凹凸を吸収します。そのため、多少の石や枝を踏んでも足裏にあまり衝撃が伝わりません。一方、Vapor Glove 6のソールは極薄でクッションもほぼないため、小石の存在さえもリアルに感じ取れるほど。
この「足裏への情報量の多さ」がベアフットシューズの最大の特徴であり、最大の違いです。
2. 足首のサポートの有無
登山靴の多くはハイカットで、足首をしっかりとホールドし、捻挫などを防ぐ設計になっています。それに対してVapor Glove 6は完全なローカット。足首のサポートはありません。その分、自由度が高く、足全体を使って歩く感覚になります。
ただし、岩場や不安定な足場では注意が必要で、慎重なステップが求められるのも事実です。
3. 重量の差

一般的な登山靴は、片足で500g〜800gほどが主流。一方、Vapor Glove 6は片足約150g前後と超軽量。まるでスニーカー、というより「裸足で歩いているような感覚」です。長時間の歩行で足への負担が軽減される一方で、クッションのない分、筋肉への負荷はむしろ増すこともあります。
4. 防水性の違い
多くの登山靴にはゴアテックスなどの防水素材が使われていますが、Vapor Glove 6には防水性はありません。水たまりやぬかるみでは、すぐに濡れてしまうのが難点。ただし、乾きは非常に早く、濡れても蒸れにくいというメリットもあります。
総じて言えるのは、Vapor Glove 6は「守ってくれる靴」ではなく、「感じさせてくれる靴」だということ。使いこなすには多少の慣れと、歩き方の工夫が必要ですが、それこそがこのシューズの魅力でもあります。
ベアフットシューズとは何か?(簡単な解説)
「ベアフットシューズ」とは、裸足(barefoot)で歩く感覚に限りなく近づけることを目的に設計されたシューズのことです。見た目こそスニーカーのように見えますが、その構造はまったくの別物。普通の靴とは根本的な発想が異なります。
ベアフットシューズの基本的な特徴

- 極薄ソール
ソールの厚さはわずか数ミリ。地面の凹凸や質感を直接足裏で感じ取れるようになっており、「歩く」という行為がまるで新しい感覚になります。 - ゼロドロップ(0mmドロップ)
つま先とかかとの高低差がない「フラットな靴底」。これにより、体本来の自然な姿勢や歩行が促されます。通常の靴ではかかとが少し高くなっているものが多いですが、ベアフットシューズではその違和感がなくなります。 - つま先が広い
足の指を自然に広げて使えるように、トゥボックス(つま先部分)はワイドな作り。足指が自由に動かせることで、バランスを取りやすくなり、安定感も増します。 - 柔らかく、しなやかな素材
アッパーやソールは非常に柔軟で、足の動きにピタッとフィット。まるで「履く靴下」とも言われるほどです。
なぜ今、ベアフットシューズが注目されているのか?

近年では、自然な歩行や体の使い方を見直す動きが活発になっており、「機能的すぎる靴が、かえって人間本来の身体機能を損なっているのでは?」という視点から、ベアフットシューズが再評価されています。
特にランナーや登山者の間では、「足本来の力を鍛える」「地面との一体感を味わう」といったメリットから導入する人が増えており、“歩く”ことの原点に立ち返るギアとして注目を集めています。
登山で実際に履いてみた!使用シーンとルート紹介
試した登山ルート(標高、地形、天候など)

私がVapor Glove 6を実際に試したのは、兵庫県の「摩耶山」です。神戸の中心部からもアクセスしやすく、登山初心者からベテランまで楽しめる人気の山。今回は摩耶山の中でも自然をじっくりと味わえるコースを選びました。
ルートは以下の通りです:
- 上野道から登り、掬星台(きくせいだい)へ
青谷登山口から登山スタート。最初は石畳が続き、その後は土と岩の混在した山道へ。標高差は約700m程度で、所々に急登もありますが、距離は比較的短め。 - 掬星台から穂高湖方面へ縦走
掬星台は神戸の街並みを一望できるビュースポット。そこからは尾根伝いに穂高湖まで進みます。湖周辺は平坦でリラックスして歩ける区間です。 - 穂高湖から「シェール槍」へ
最後は少しマイナーなルートで、岩場も点在する「シェール槍」へ向かいました。大きな岩もあり、Vapor Glove 6のグリップ力や足裏感覚をしっかりと試せるセクションでした。
どういう条件で履いたのかを具体的に

この日は3月下旬、春らしいぽかぽかとした陽気で、3月とは思えないほど暖かく、非常に快適な登山日和でした。天候は晴れで、前日も雨は降っておらず、登山道のコンディションも良好。土の部分は乾いており、滑るような場所もほとんどありませんでした。
服装は軽装で、荷物も必要最低限。足元には、今回が初使用となるMERRELL Vapor Glove 6を着用。インソールは純正のままで、ソックスはG.Uで購入したごく普通の靴下。特に登山用でもベアフット専用でもなく、日常使いの薄手ソックスです。
このシンプルな組み合わせが、かえって足裏感覚をダイレクトに伝えてくれる環境となり、Vapor Glove 6の魅力をよりリアルに体験できました。
一番の驚きは「地面を感じる楽しさ」
足裏で感じた岩や土、草の感触

Vapor Glove 6を履いて歩き出してすぐに感じたのは、足裏から伝わる地面の感触がとても鮮明だということでした。普段履いているトレランシューズでは、道の状態を「なんとなく」足で感じ取っていたのに対し、ベアフットシューズでは、土のざらつきや岩の硬さ、小石の存在までがリアルに伝わってくるのです。
上野道は比較的歩きやすいルートですが、それでも場所によっては岩っぽい箇所や砂利、乾いた土の道など、地面の質感はさまざま。こうした変化が一歩一歩、ダイレクトに足裏に響いてくるのは、これまでの登山靴では味わえなかった新鮮な感覚でした。
地面との一体感がもたらす新しい登山体験
通常の登山靴では、厚めのソールやクッションによって足がしっかりと守られている分、地面との間に一枚“フィルター”がかかっているような感覚があります。しかしVapor Glove 6ではそのフィルターが取り払われ、まるで自分の足が直接自然の上を歩いているかのような一体感がありました。
岩場ではその硬さ、平坦な土道では粒子の細かさ、少し乾いた小枝の上では「パキッ」という感触まで感じ取れ、それがとても面白い。まるで、足が“センサー”になったかのような感覚です。
五感をフルに使う感覚の面白さ

今回の登山では、「歩く」という行為に対する意識が明らかに変わりました。足裏の感覚に集中することで、身体全体が地形に反応しているような感覚になり、無意識に丁寧な歩き方になっていたのです。
これまで“無難に通過していた道”が、“意識的に味わう道”へと変わる体験。音や匂い、景色といった従来の感覚に加えて、「触れる」登山ができるようになった感覚は、まさにベアフットシューズの醍醐味だと思います。
メリットとデメリットを正直レビュー
実際にVapor Glove 6を履いて摩耶山を歩いてみて感じたのは、「楽しい!」という感覚と同時に、「これは万人向けではないかも」というリアルな気づきでした。ここでは、実際に登山で使って感じた良かった点と気になった点を、正直にレビューしてみたいと思います。
良かった点:軽さ、自由な足の動き、自然との一体感
■ とにかく軽い

Vapor Glove 6の圧倒的な軽さは、歩き始めてすぐに実感できます。片足150gほどという数字は正直ピンと来ないかもしれませんが、実際には「何も履いていないのでは?」と錯覚するほど。足取りが軽く、登りでもストレスが少ないです。
■ 足の動きが自由になる
クッションやサポートが最小限だからこそ、足が本来の可動域で自由に動くのが分かります。足の指で地面をつかむように歩く感覚が新鮮で、身体全体でバランスをとる感覚が強まりました。これにより、普段あまり使わない筋肉が自然と働くのも面白いポイントです。
■ 自然との一体感がある
「地面の感触を足裏で感じながら歩く」というだけで、登山そのものがもっと感覚的で、没入感のある体験になります。音や匂い、景色に加えて、足裏という“もうひとつのセンサー”が増えることで、まさに五感で山を楽しむことができました。
気になった点:足裏の疲労、耐久性
■ 足裏へのダメージは覚悟が必要
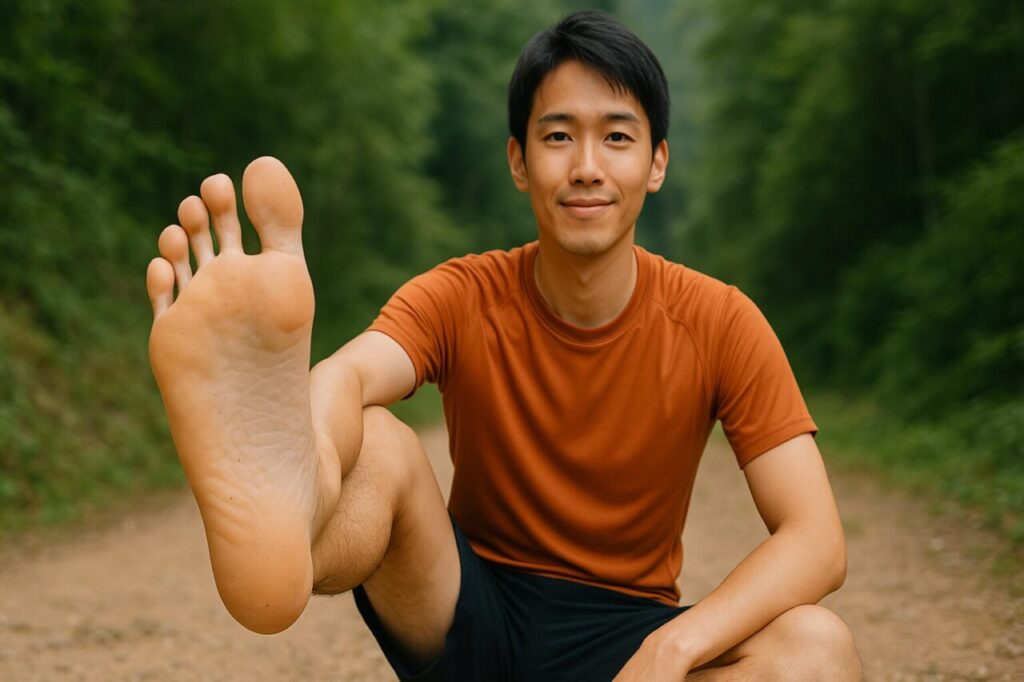
クッション性がほとんどないため、歩き方に慣れていないと足裏がかなり疲れます。今回は整備された登山道が多かったので問題ありませんでしたが、ゴツゴツした岩場や長時間の行動では、ダイレクトな衝撃が蓄積されそうです。筋力のない初心者がいきなり長時間履くにはややハードルが高いと感じました。
■ 耐久性には注意が必要かも
ソールが薄く柔らかいため、ガレ場や鋭利な岩場では摩耗しやすい可能性があります。また、足全体を保護する機能は少ないので、擦れや突き上げによる痛みにも注意が必要。ハードな環境での使用には向いていないかもしれません。
初心者には向く?向かない?

正直に言うと、登山初心者がいきなりこれ一足で山に入るのはあまりおすすめできません。足の使い方やバランス感覚がある程度備わっていないと、思わぬ怪我につながる可能性もあります。
ただし、普段から歩き慣れていて、軽登山や低山ハイクを楽しむ方であれば、Vapor Glove 6は非常に魅力的な選択肢になります。体への負荷を感じながら、「自然とつながる登山」を楽しみたい人には、ぜひ一度試してほしい一足です。
結論:ベアフットシューズは「冒険心」を呼び覚ますギアだった
登山スタイルが変わる可能性
今回、初めてベアフットシューズを使って登山をしてみて感じたのは、これまでの登山の常識が少しずつ揺らいでいくような感覚でした。今まで当たり前だった「厚底」「サポート」「保護」といった要素がなくても、山は歩ける。そして、むしろそれが新しい気づきや楽しさにつながる。
Vapor Glove 6を通して、「登山はもっと自由でいい」という思いが強くなりました。必要以上に装備に頼らず、自分の身体の力を使って自然の中を歩く。このスタイルは、私の登山観に新しい視点を与えてくれました。
これからの使い方やおすすめしたい人

Vapor Glove 6は、毎回の登山で使うというよりも、「今日は感覚を楽しみたい」「のびのびと自然と向き合いたい」という日に選びたくなるシューズです。天候が良く、比較的歩きやすいルートであれば、積極的に使っていきたいと思います。
おすすめしたいのは、以下のような人たちです:
- 普段から軽装で登山をしている人
- トレランやハイキング経験があり、足の感覚に意識が向いている人
- 五感を使った登山や“没入感”を求めている人
- 「山をもっと自由に楽しみたい」と感じている人
逆に、岩場が多い山や長時間の縦走、悪天候が予想される場面では、これまで通りの登山靴を選ぶのが安心です。つまり、「選択肢の一つとしてのベアフットシューズ」という立ち位置がちょうど良いのかもしれません。
次はどんなルートで試したいか

今回の摩耶山での体験を経て、「もっといろんな地面を歩いてみたい」という気持ちが強まりました。次に試したいのは、もう少し標高が高く、土や岩、木道など地形のバリエーションが豊富なルート。たとえば六甲全山縦走の一部や、奈良の大峯奥駆道あたりも面白そうです。
また、キャンプ場での散策やトレイルウォーキングなど、登山よりも気軽なアウトドアでも使ってみたいと思います。街歩きとの相性も良さそうなので、旅行時のサブシューズとして持って行くのもアリかもしれません。
ベアフットシューズは単なる「靴」ではなく、感覚を研ぎ澄まし、自然との距離を縮めてくれるギアでした。ちょっとした冒険心と一緒に、この一足をザックに入れて、次の山へ出かけたくなる——そんな存在です。
▼MERRELL「VAPOR GLOVE 6」はこちら▼
▼おすすめの記事はこちらから▼